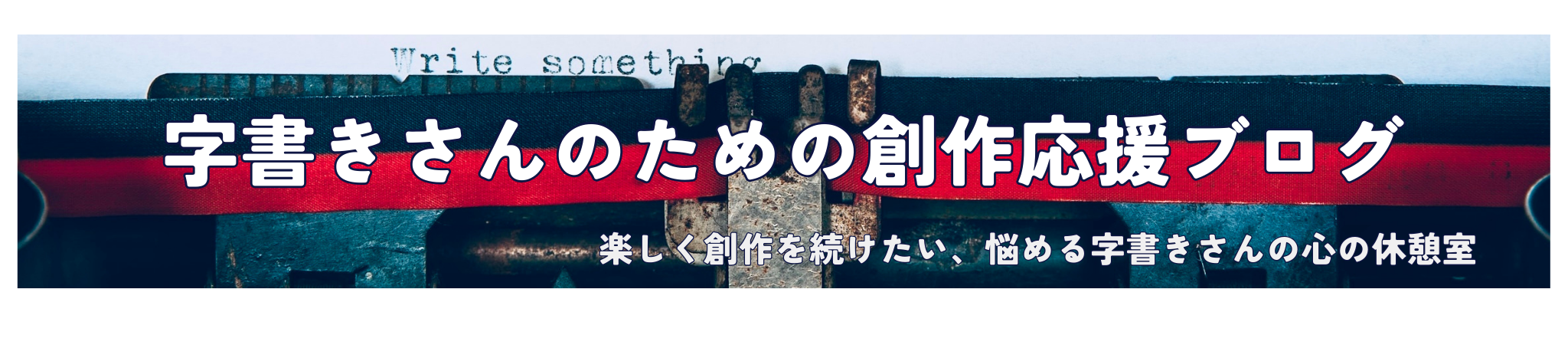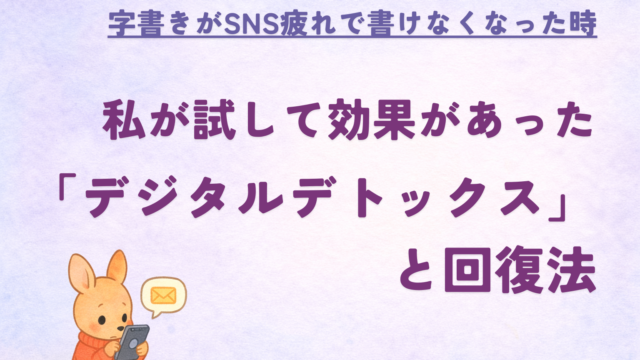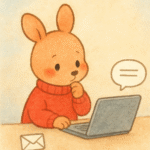「誰にも読まれていない気がする」と落ち込む字書きへ。感想ナシ・反応ゼロでもあなたの作品に価値がある理由
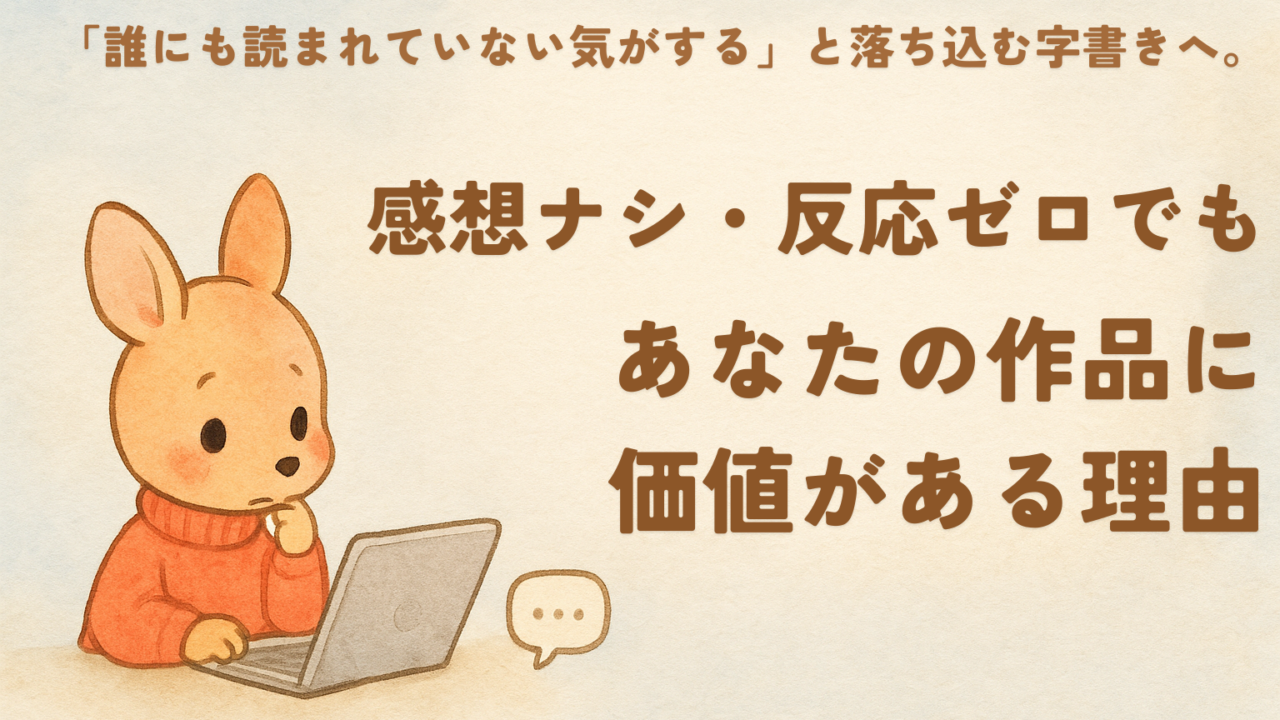
一生懸命頭をひねって書いた小説に何の反応もないと、誰からも必要とされていないような孤独感に襲われてしまいませんか?
ちょっとでも感想が欲しかった……
もう私が書かなくたって誰も気にしないんだろうな
「この話、絶対面白い!」と信じて時間をかけて書いたのに、ブックマークは一桁、感想はゼロ……。
そんな時、「私の小説、誰かに届いてほしかったな」と、がっくりしてしまう辛さは、同じ字書きとして痛いほどよくわかります。
でも、どうかこれだけは信じてください。
「反応がない」ということと、「あなたの作品に価値がない」ということは、全く別の話です。
この記事では、反応ゼロで筆を折りかけた私が立ち直るきっかけになった、「創作の本当の価値」についての考え方をお伝えします。
なぜ私たちは「感想」をこれほど渇望するのか?
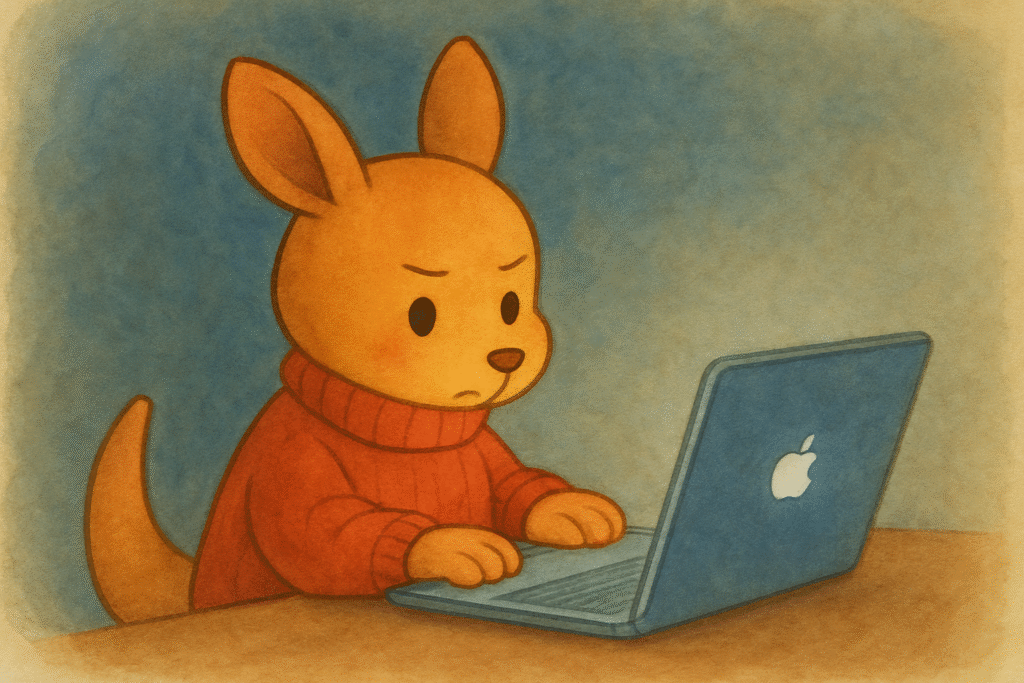
1. 頑張った「証拠」が欲しい
ダイエットなら体重計の数字、勉強ならテストの点数で成果が見えます。
しかし、創作には明確なゴールがありません。
「2ヶ月かけて書いたこの時間は無駄じゃなかった」と証明してくれる唯一のものが、他者からの反応に見えてしまうのです。
2. 「孤独」を埋めたい
一人で黙々と文章に向かう作業は孤独です。
この萌えを共有したい!
同じような妄想をしている仲間が欲しい!
感想を求めるのは、決してわがままではなく、「誰かとつながっていたい」という人間として当たり前の心の動きなのです。
まずは、「感想が欲しいと思ってしまう自分」を責めないであげてください。
それはあなたが作品と真剣に向き合っている証拠なのですから。
感想がもらえなくても「作品に価値はある」3つの理由
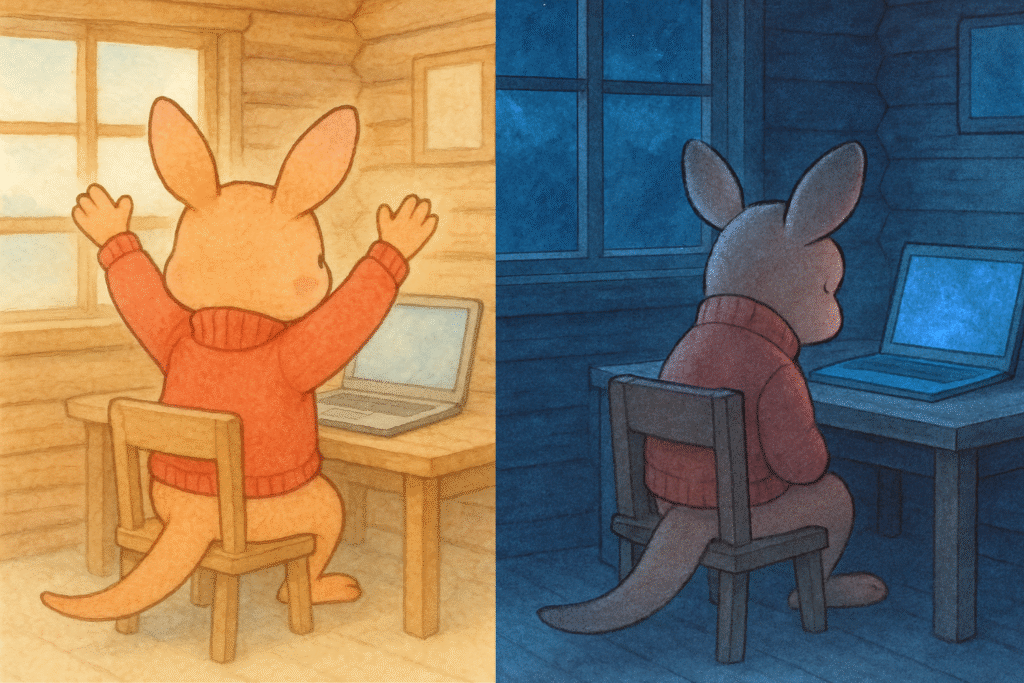
「反応ゼロ=ゴミ」だと思い込んでいた私ですが、冷静に分析してみると、それは大きな間違いであることに気づきました。
理由1:読者の9割は「サイレント読者」だから
ネット上で記事や小説を読んだ人のうち、実際に反応(いいねやコメント)をするのは、わずか1割程度と言われています。
特に二次創作の場では、「感想を送る勇気がない」「どう言葉にすればいいかわからない」という「サイレント読者」が圧倒的多数です。
数字として表れていなくても、あなたの作品を読んで「ああ、いいな」と静かに心を動かされた人は、画面の向こうに確かに存在しています。
理由2:価値は「今すぐ」には決まらない
私が投稿当時、全く反応がなかった作品について、数年後に「この作品がずっと大好きで、何度も読み返しています」というメッセージをもらったことがあります。
作品の価値は、投稿した瞬間の初速だけで決まるものではありません。
誰かの人生のタイミングと合った時に、初めて宝物になる。
そんな「時間差の価値」が創作にはあります。
理由3:最大の価値は「あなたが形にした事実」にある

最も大切なのは、あなたの頭の中にしかなかった「妄想」や「感情」を、文字という形にしてこの世に生み出したことです。
- 自己表現をしたこと
- 完結まで書ききったこと
- 文章力が(自分では気づかないうちに)向上したこと
これらは、他人の評価に関係なく、あなたの手の中に残る確かな財産です。
苦しい時は「自分の気持ち」を書き出してみよう

それでも、「やっぱり辛いものは辛い!」という時は、その気持ちを紙に書き出してみてください。
- 「感想が欲しい!悔しい!」と本音を書きなぐる
- 「なぜ?」と問いかけて掘り下げる(例:あの人に負けたくないから、寂しいから)
頭の中でぐるぐると考えているモヤモヤを、文字にして外に出す(可視化する)だけで、不思議と心は落ち着きます。
これは「エクスプレッシブ・ライティング(筆記開示)」と呼ばれる心理療法の一つでもあり、誰にも見せない紙の上なら、どんな黒い感情を吐き出しても自由です。
まとめ:あなたは一人じゃない
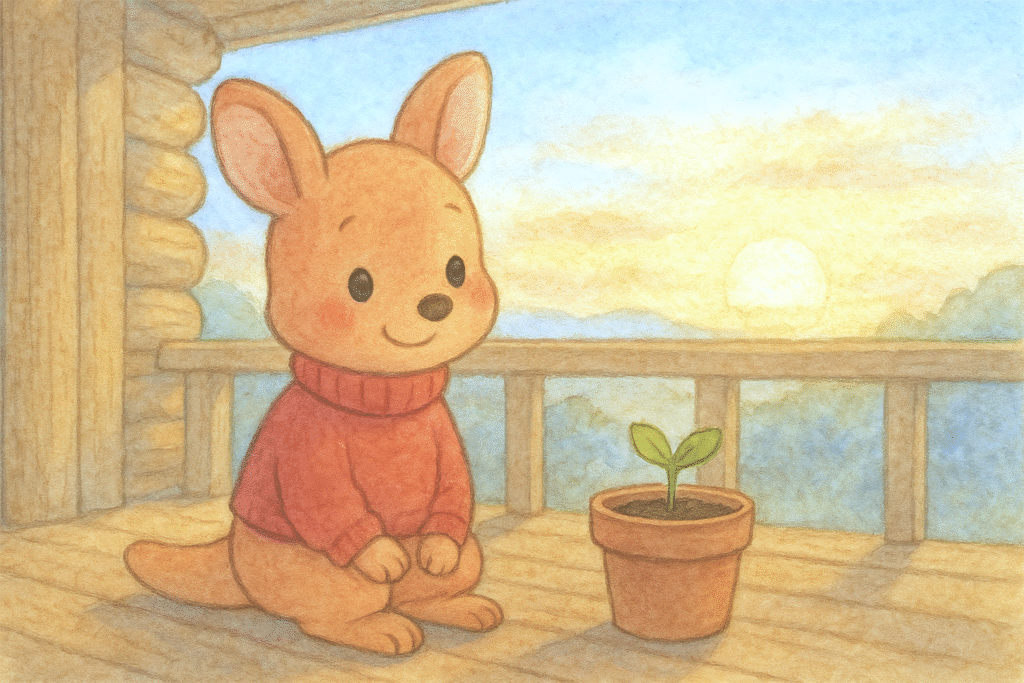
数字や反応は、創作の「おまけ」のようなものです。
もちろん、おまけがたくさんあれば嬉しいけれど、それがなくても、メインである「あなたの作品」の味や価値は変わりません。
どうか、誰にも見つけられなくても、あなた自身だけは「よく書いたね」と自分を褒めてあげてください。
あなたが書いたその物語は、あなたにとってかけがえのない大切な世界なのですから。
一人で抱え込まず、話してみませんか?

頭ではわかっていても、やっぱり心が晴れない
誰かに話を聞いてほしいけど、身近な人には言えない……
そんな時は、一人で抱え込まないでください。
私は現在、ココナラで「創作活動の悩み相談」を受け付けています。
同じように数字に苦しみ、筆を折りかけた経験がある字書きとして、あなたの気持ちに寄り添い、お話をお聞きします。
アドバイスが欲しいわけじゃなく、ただ「辛い」と言いたいだけでも大丈夫です。
あなたの創作の灯が消えてしまう前に、よかったら少しだけ、荷物を下ろしに来てくださいね。
創作は時に孤独で、出口が見えなくなることもあります。
でも、あなたの気持ちはすべて無駄じゃない。真剣に向き合っているからこそ生まれた、大切な感情です。
どうか、書いた自分に誇りを持って。そして、また書ける日を、少しずつ、一緒に探していけたら嬉しいです。